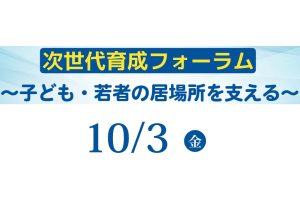2025年度助成先が決まりました
「子ども/若者ライフサポートプログラム」第3回助成の審査を行い、 下記の通り決定いたしました。
助成先一覧
■継続助成
| 団体名 | 所在地 | 事業名 | 助成額 |
|---|---|---|---|
| 特定非営利活動法人 ASTA | 愛知県 | LGBTQ+出張授業&名古屋あおぞら部 | 200万円 |
| 特定非営利活動法人 茨城居場所研究会 | 茨城県 | ひきこもりがちな若者の居場所づくり事業 | 190万円 |
| 特定非営利活動法人 青少年自立支援施設淡路プラッツ | 大阪府 | ひきこもりの若者とご家族のための「居場所」と「相談できる場所」をつなぐ事業 | 216万円 |
| 特定非営利活動法人 ほっこりスペースあい | 京都府 | 不登校・ひきこもり当事者、家族、関係者への相談と居場所支援事業 | 250万円 |
| 一般社団法人 officeひと房の葡萄 | 兵庫県 | 困難を抱えた子ども/若者の社会的居場所「ぐれいぶハウス」の継続。安定化事業と高校卒業後の自立支援事業 | 231万円 |
| 特定非営利活動法人 よりみち | 和歌山県 | 地域の居場所「よりみち文庫」をプラットホームに~不登校・引きこもり支援事業 | 155万円 |
| 特定非営利活動法人 ブエンカミーノ | 広島県 | 子どもサードプレイス「安佐北フリースクールOKAZAキッズ」 | 250万円 |
| 一般社団法人 カザグルマ | 千葉県 | 子どもの居場所カフェ | 160万円 |
| 特定非営利活動法人 Since | 滋賀県 | 新たな居場所を作る!出張フリースクールを通した他地域展開事業 | 250万円 |
| 特定非営利活動法人 メロディー | 香川県 | 「フリースペースじゆうだ」をさらにユニバーサルな居場所に変革させる事業 | 168万円 |
*助成期間:2025年10月1日から2026年9月30日までの1年間
*助成件数:10件
*助成総額:2,070万円
選考総評
1.選考委員会 総評
2025年度は、「子ども・若者ライフサポートプログラム」の最終年度となります。そのため、今回は継続団体のみを対象に募集を行いました。
書類審査および選考委員会でのプレゼンテーションを経て、選考を実施しました。継続助成であることから、これまでの助成プログラムにおける実績の提示、課題の振り返り、そしてそれらを踏まえた発展・改善の内容が示されているかどうかを重視して議論を行いました。また、助成終了後も活動が持続可能であるかという視点も重要な評価項目としました。
その結果、支援活動のさらなる発展・改善が期待される10団体を継続助成団体として採択いたしました。
採択団体に共通して見られた点としては、声をあげにくい子ども・若者にリーチするためのさまざまな工夫がなされていること、そして利用者の状況やニーズに応じて活動内容を柔軟に変化させる取り組みが行われていることが挙げられます。
本助成による成果が、各地で同様の活動に取り組む団体にも共有され、全国的なモデルとして広がっていくことを期待しています。
助成概要と推薦理由
■継続助成
助成事業テーマ「LGBTQ+出張授業&名古屋あおぞら部」
ASTAは、性的少数者(LGBTQ+)の人権や多様性に関して出張事業や研修などの啓発活動を行っている。愛知県内外で生活する当事者や当事者かもしれない若者に対する相談とピアサポートの場「名古屋あおぞら部」は、性の多様性を尊重し、スタッフ配置で性のあり方に偏りがないよう配慮もしており、当事者たち自らでつくるサードプレイスとなっている。出張授業を受けた生徒があおぞら部に参加するケースは多く、あおぞら部でロールモデルと出会い、伴走支援を経て、あおぞら部のスタッフとなる循環を目指している。
前年助成では、自分らしい姿での門出を祝えるLGBTQ+成人式の実施や、低年齢の子どもに遠すぎない地域に場づくりすることを目指し、岐阜での「あおぞら部」開催に至ったことを評価したい。今年度の助成では、当事者が安心して集える場が少ない過疎地でのLGBTQ+出張授業を増やすこと、愛知県外で「あおぞら部」を継続開催する地元の体制づくりが計画されている。当事者の孤立を防ぎ、LGBTQ+の理解促進のためにも、ピアサポートの居場所を種まきし、それぞれの地域特性も踏まえて定着させていく事例の蓄積が求められる。
性の多様性に対する学校現場での啓発ニーズが高まる一方で、啓発のための公的財源確保は不十分であり、ASTAは重要な役割を果たしている。活動の持続性を高められるよう、成果や意義を整理、発信することも期待したい。
助成事業テーマ「ひきこもりがちな若者の居場所づくり事業」
茨城居場所研究会は、茨城県県北地域を中心に、ひきこもりがちな若者の居場所づくりと、地域の理解を促進する啓発活動を通じて、誰もが過ごしやすい社会の実現を目指している団体である。
活動エリアにおいては、ひきこもりがちな若者に限らず、若者が気軽に利用できる居場所がほとんど存在していないのが現状である。NPOによる居場所の運営は、若者がアクセスしやすい環境づくりに大きく貢献するものである。 これまで、居場所の開設に加え、映画上映会や研修会などのイベントを実施してきた実績があり、地域の住民からの認知も広がりつつある。今年度も活動を継続することで、居場所の役割が地域に定着し、新たな担い手の育成につながる機会となることが期待される。
■特定非営利活動法人青少年自立支援施設淡路プラッツ(大阪府)
助成事業テーマ「ひきこもりの若者とご家族のための「居場所」と「相談できる場所」をつなぐ事業」
淡路プラッツは30年以上にわたり、ひきこもりや不登校などで孤立する若者とその家族に寄り添い、安心できる居場所と相談支援を提供してきた。近年は、より自立した暮らしを意識した支援や、就労支援に向けたパートナー拡充など、活動の発展性も見られる。また、日常生活体験の訓練においても、実践を振り返り常に工夫を加えながら、より良い支援を模索している点が印象的である。
ひきこもり支援は短期的な成果が見えにくいが、社会的に継続的な解決が求められる課題である。そのなかで淡路プラッツの取り組みは、堅実で持続可能な活動として地域で確かな役割を果たしている。今後も若者や家族が安心できる仲間と出会い、自らの力を取り戻し、社会とのつながりを築いていけるような取り組みへと、さらに発展していくことを期待したい。
助成事業テーマ「不登校・ひきこもり当事者、家族、関係者への相談と居場所支援事業」
ほっこりスペースあいは、2001年に不登校の子どもや青年の居場所を地域につくりたいと願う親たちによって開所された団体である。以後、約350人に対する相談対応や居場所支援を実施し、回復への歩みを応援してきた実績を有する。
これまで、行政のひきこもり支援事業を受託し、当事者や家族との継続的なつながりを重視した支援活動と、地域ネットワークの構築に取り組んできた。
今回の助成では、特に就労の定着支援や就労先との連携、新たなネットワークづくりにおいて、地域におけるNPOと企業の実践事例として、全国的なモデルプログラムへの発展が望まれる。
また、専門機関や親の会との連携・協力により、当事者や家族に対する重層的な支援の展開が期待される。
助成事業テーマ「困難を抱えた子ども/若者の社会的居場所「ぐれいぶハウス」の継続。安定化事業と高校卒業後の自立支援事業」
officeひと房の葡萄は、家庭でケアをされていない子どもたちの存在に注目し、誰もが安心して過ごすことができる居場所づくりをしている。これまで、子ども・若者のみならず若年女性や母子など、支援が必要な対象に継続的に支援を行ってきた実績がある。
こどもの社会的居場所事業は、⾧期間にわたって何らかの困難を抱える子どもと関係性を築いていける場所として運営されている。特に、昨年スタートした夜間の居場所である「ナイトぐれいぷ」は、家に帰ることができない若者たちの居場所として、大切なものとなっている。他にも、自立支援型シェアハウス「ますかっと」は若者に自立のスキルを身につけてもらう場所として設けられている。さまざまな課題を抱えた若者たちに対して、多様なアプローチで支援活動が展開されていることを評価した。若年女性の支援モデルとして、全国的な発信も期待したい。
助成事業テーマ「地域の居場所「よりみち文庫」をプラットホームに~不登校・引きこもり支援事業」
「よりみち」は、さまざまな困難を抱えていることにより、一般就職などの形での社会的自立が難しい方々を対象とした支援を実施しており、近年の8050問題に対応する取り組みであると言える。ひきこもりや不登校を経験した当事者のなかには、メンタルヘルスの不調があることも少なくないが、本人から支援のニーズを発信することが難しい場合、親や家族からの相談を通じて支援につなげることが必要となる。「よりみち」は、保健師やソーシャルワーカーなどの専門性のあるスタッフと地域の多くのボランティアが関わっており、地域のなかで支援ニーズがある方の掘り起こしや、支援につながったあとの継続的な見守りが可能となっている。
運営する「街角ライブラリー」は、誰もが気軽に訪れやすいよう、支援する人/される人という形をとっておらず、支援ニーズのあると思われる方の特技を生かした活動を展開するなど、当事者の持つ強みを引き出すような取り組みを行っている。当事者や家族の思いを理解しようとするために時間をかけ、ていねいに関わっているからこそ、このような活動が可能となっていると思われる。 このような、専門職、ボランティア、地域住民が関わることができる居場所は、今後ますます重要になると考えられる。地域に根差したNPO法人による活動のあり方としてモデルケースの1つになることが期待される。
助成事業テーマ「子どもサードプレイス「安佐北フリースクールOKAZAキッズ」」
ブエンカミーノは共同生活と農業を主とした若者自立支援事業を行う団体で、「コミュニティカフェ岡崎キッチン」を運営している。初年度助成で、カフェスペースの一部を活用し、不登校の子どもを受け入れるフリースクールを開設した。
2年目助成では、外遊びを可能とする敷地内の運動場・野外炊事場を整備し、子どもが自信をつけるための学び環境を整えて、子どもたちの意欲を引き出し、学習支援の習慣を定着させてきた。発達特性のある子どもには、障害児用の教材やツールを活用し学習に慣れる時間をつくってきた。専門機関連携の参与観察などで、特性のある子どもの保護者へのフィードバックを含む支援が行えている。活動の課題検討プロセスに親や子どもの参加の機会を設けていることも評価したい。
今年度助成では、学習支援体制のさらなる強化、進路決定を視野に入れ、子どもの興味関心に応じた職業体験、SSWとの連携や地域社会に対するフリースクールの認知度向上の取り組みが計画されている。 フリースクール併設のカフェという敷居の低さは強みであり、不登校親子のカフェ利用が増えている。身構えずにスタッフに不登校について話せたり、食後に子どもが外遊びに加わる様子が見られることは、好ましい変化と言える。当事者のペースや意志を尊重しながらも、見学から入会へつなぐための検討や必要な支援につなぐ働きかけを続け、安定運営を可能にする財源獲得の仕組み構築にも期待したい。
助成事業テーマ「子どもの居場所カフェ」
カザグルマは、経済的に困難な家庭や多文化背景のある子どもが多い地域で、安心して過ごせる居場所と食事支援を提供し、現代社会において必要性の高い活動を展開している。年間300日以上開所し、地域の学校や行政、医療機関と連携しつつ、フリースクールや農業体験など、さまざまな学びや体験の機会も提供し、地域の居場所として定着しつつある。
本年度は新たな取り組みとして放課後等デイサービスを開始し、障がい児や支援対象外の子どもたちへの支援も拡充した。さまざまな子どもが安心して過ごせる居場所づくりを目指し、各種支援を受けながら自主的な運営で事業を着実に広げ、利用者数も増加している。今後は、事業運営の基盤をさらに整え、幅広い子どもたちを支えながら、地域において信頼される居場所としてさらに定着することを期待したい。
助成事業テーマ「新たな居場所を作る!出張フリースクールを通した他地域展開事業」
Sinceは若者が中心となって立ち上げたNPO法人であり、地域交流や連携促進の取り組みを精力的に行うフリースクールである。定期的なフリースクール開設に加えて、不登校フォーラムの開催や地域住民とのマルシェ企画・運営、小学校内での水遊びパークを実施するなど、子どもの成長を地域の人々とともに育むという視点を大切にしている。
利用者の約7割は、近隣の他市からの参加である。その理由として、近隣のフリースクールには通いにくいという心理的要因が考えられる。そのため、通学に 1 時間以上をかけている子どもも多くいる。電車利用ができるほど、エネルギーが回復していることが求められる。フリースクールへのアクセスの問題により、参加できない子どもが存在している。今回の助成では、フリースクールを他地域で出張的に展開し、通いにくい子どもたちへアプローチする取り組みが行われる。子どもたちのニーズに応じて、活動を柔軟に変化させ、常に新たなチャレンジに取り組む姿勢を評価した。
助成事業テーマ 『「フリースペースじゆうだ」をさらにユニバーサルな居場所に変革させる事業』
メロディーは、子ども・若者のための居場所を運営している。「フリースペースじゆうだ」は、自分に合った過ごし方ができる居場所であり、「Social Space Melody」は、地域の人々とともに発信者としてチャレンジできる居場所である。地域性を考慮すると他に類似する居場所が豊富にあるとは言えないなかで、子ども・若者が自分に合った居場所を選ぶことができるという点はたいへん重要である。
法人としては、2007年より障害のある子どもの支援を行ってきた。今回の申請では、障害の有無にかかわらず、対人関係や学習等で困難を抱えているすべての子どもたちが、楽しいと思える活動や自信を持つことにつながるような活動を経験できる居場所を発展させるためのものである。具体的には、これまで行ってきた安心できる居場所づくりに加え、高校生以上の若者も含めた年齢に応じた切れ目のない継続的な支援や、より専門的な対応が求められる子ども・若者へのアプローチを意図している。また、福祉的ニーズのある子ども・若者に対する事後対応ではなく事前予防にもつなげることを目指している。新たに開設する居場所を商店街にすることにより、多世代で地域との交流を深めながら、活動が活性化することが期待される。